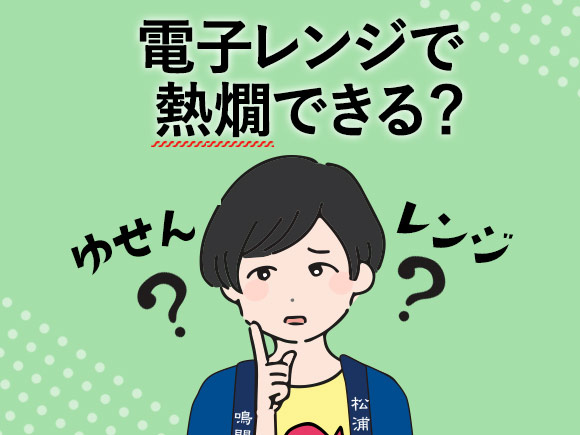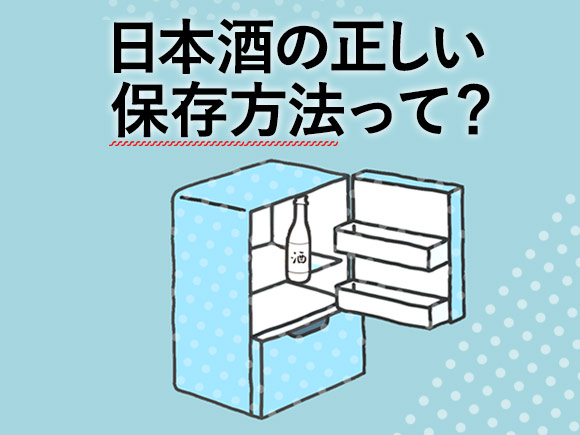地鎮祭のとき、祭壇におまつりする日本酒を「奉献酒」といいます。
どんなものを用意すればいいのでしょうか?
ズバリ、「奉献酒」は一升瓶1本、あるいは一升瓶2本箱が主流です!
この記事では、その理由や一般的な地鎮祭の基本についてご紹介しますね。

こんにちは。親が家を建てることになりました。
地鎮祭のときに日本酒を用意するように頼まれました。どうしたらいいですか?

「奉献」と書いたのし紙を巻いた日本酒を用意したらいいですよ。
いわゆる「奉献酒」です。

そうなんですね。わたしは地鎮祭を見たことがなくて。

なるほど。地鎮祭を見る機会はなかなかありませんよね。
阿波一宮 大麻比古神社の神職、岩野権禰宜(ごんねぎ)さんにお話を聞いてみましょう。

「奉献」あるいは「奉納」の熨斗をした日本酒をお供えします

はじめまして。よろしくお願いいたします。
「奉献酒」や「地鎮祭」のことを教えてください。

こんにちは。大麻比古神社の神職をしている岩野です。
神さまにお供えする日本酒を「奉献酒」あるいは「奉納酒」といいます。
熨斗(のし)に書く言葉としては「奉献」「奉納」どちらでも大丈夫ですよ。
「奉献酒」とは、神さまにお供えする日本酒のことです。
奉献とは『神仏や目上の人に謹んで献上すること』を意味します。
一般的に、日本酒の瓶に「奉献」と書いた熨斗(のし)紙を巻いたものを用意し、地鎮祭の祭壇におまつりします。
神社でも奉献酒をおまつりしている様子をご覧になったことがあるかもしれません。

当蔵の定番酒に「奉献」の熨斗をお付けしました。金色の巻紙の一升瓶はおめでたい場にぴったり。本家松浦酒造場の「奉献酒」をどうぞご利用ください。300ml 2本のミニサイズ奉献酒もどうぞ。
地鎮祭とは、土地の神様にご挨拶する儀式
地鎮祭(じちんさい)は「地鎮祭(とこしずめのまつり)」や「地祭り(じまつり)」とも言われ、建築の際の重要なお祭りです。
工事を始める前に、その土地の神さまにご挨拶し、土地を祓い清め、これから行われる工事の安全と、その土地で暮らす人々の繁栄を祈るものです。
建設予定の敷地のなかに祭壇を設け、お供物をし、その土地の神さまをお迎えします。
家とは神様をお迎えする大切な場所でもあります。地鎮祭は、家を建てるときの工事の安全や無事を神様に祈る大切な神事なのです。


個人住宅の地鎮祭の場合、奉献酒はどんなものが多いですか?
「奉献酒」は、一升瓶2本組、あるいは一升瓶1本が主流
地域によって異なるとは思いますが、
一升瓶2本組または1本をお供えしていることが多いです。
「奉献」または「奉納」の熨斗(のし)を付けてもらいましょう。2本組の場合は縄で縛って熨斗をかける場合や、化粧箱に熨斗をかける場合があります。

奉献酒については建主さんが用意される場合もありますし、建築家さん、建設会社さん、大工の棟梁さんなど、関係者の方が用意される場合もあります。
また、建主さんの親戚の方などが奉献酒をお持ちになっている様子もたまにお見かけします。
まずは施工の担当者さんやご家族と相談したらいいと思います。
神様への感謝の心が伝わればOK
例えば、当神社へいつも月参りにいらっしゃる方々がいらっしゃいます。
その方々は、お米、お酒やお野菜などをお供えしてくださるのですが、一升瓶だったり、ワンカップだったり、ご自分で作られたお米やお野菜だったりと・・・実に様々です。

神様に感謝の心をお伝えするためのものですから、どんな大きさでも、どんなかたちでも、気にする必要はないと思いますよ。

地鎮祭で用意するもの
建設予定地の四隅に青竹を立てて、しめ縄で囲むようにして祭場をつくります。
その中に設えた祭壇に、米、清酒、魚、海藻類(昆布、海苔、寒天など)、野菜、果物、塩、水などの「神饌」などをおまつりします。
あとは、盛り砂、鎌(かま)、鍬(くわ)、鍬(すき)などが必要ですが、通常は施工の皆さんが用意してくれるようです。


ちなみに、地鎮祭はどんなことをするのでしょう?
一般的な地鎮祭の流れ
地鎮祭当日は、一般的にこのような流れで儀式を行います。
- 1.修跋(しゅばつ)
神主さんが、参列した人やお供物を祓い清めます。 - 2.降神(こうしん)
神籬(ひもろぎ)に神様をお迎えします。 - 3.献饌(けんせん)
神様のお食事である神饌(しんせん)をお供えします。
※神饌とは、神様へのお供え物のことで、神様のお食事です。米、酒、魚、海藻、野菜、果物、お菓子、塩、水などを供えるのが一般的です。 - 4.祝詞奏上(のりとそうじょう)
氏神様、土地の神様に工事することを奉告し、お祈りの言葉を申し上げます。 - 5.散供(さんく)
米、塩などを土地の神様にお供えし、祓い清めます。 - 6.刈初(かりぞめ)・草刈初(くさかりぞめ)・鍬入れ(くわいれ)
土地に鎌・鍬・鋤を入れます。一般的に、鎌は設計者が、鍬は建主が、鋤は施工者が、「エイエイエイ」と3回唱え、砂を崩す動作を行います。 - 7.鎮物埋納(しずめものまいのう)
土地の神様へのお供物を土の中に埋めます。 - 8.玉串拝礼(たまぐしはいれい)
玉串をお供えして拝礼します。
※玉串とは、榊などの常緑樹の小枝に紙垂をつけたものです。神様に拝礼する際は、両手で玉串を持ち、茎を祭壇に向け、真心を込めて捧げます。 - 9.撤饌(てっせん)
お供えした神饌をお下げします。 - 10.昇神(しょうしん)
お迎えした神様をお送りします。 - 11.直会(なおらい)
参列したみなさんで、お下げした神饌をいただきます。
1〜11までで、かかる時間は30分程度です。準備から入れると約1時間くらいになります。
施主さんがすることは2つ。刈初と玉串拝礼です
神主が、参列した人やお供物を祓い清めたり、祝詞を申し上げている間は、施主さんやご家族の皆さんは見守っていれば大丈夫です。
施主さんが行うことは主に2つです。
一つは、盛り砂に鎌・鍬・鋤を入れる「刈初(かりぞめ)」、もう一つは、玉串をお供えして拝礼する「玉串拝礼」の2つです。
その際には施主さんにお声掛けがありますので、アドバイスに従ってくださいね。


エイエイエイと声をかけて鍬入れするんですね。テレビで見たことがあるような。
ちょっと楽しみになってきました!
直会(なおらい)は省略される場合も
地鎮祭が無事に終わったら、神前からお下げしたお神酒や神饌(供え物やお酒)をいただく「直会(なおらい)」という行事もあります。
神さまと一緒に、お神酒や神饌をいただくことで、神霊との結びつきを強めるなどの意味があります。
一般的には神事のあとの飲食会を表す言葉でもありますが、最近では省略される場合も多いようです。
その場合は、神饌を参加者で分けて持ち帰ったりします。

地鎮祭を行うタイミングはいつですか?
地鎮祭を行うタイミングは、基礎工事を始める前
家の基礎工事を始める前に行うのが一般的です。
冠婚葬祭と同じように、縁起の良いお日柄を選んで行う場合もありますし、お仕事などで忙しい場合は関係者が揃う調整して日程を決めているようです。

ちなみに地鎮祭には、どのような服装がふさわしいでしょうか?
スーツやワンピなど、きちんと感のある服装で
土地の神様にご挨拶する日ですから、失礼のない服装がよろしいかと思います。
礼服を着る必要はありませんが、スーツ、ジャケット、ワンピースなどのきちんと感があり、清潔感がある服装をおすすめします。学生さんの場合は制服で出席したらいいでしょう。

なるほど!よくわかりました。
きちんとした服装で参加したいと思います!ありがとうございました。
本家松浦酒造場の奉献酒
本家松浦酒造場では、瓶2本を縄で縛る「奉献酒」をご用意しています。
大きさは一升瓶(1800ml)、四合瓶(720ml)、ミニサイズ(300ml)の3種類からお選びください。
それぞれ「奉献」の熨斗紙を無料でお付けします。
それぞれ箱入りの奉献酒もご用意できます。オプションで箱をお選びください。
※箱入りをご希望の場合は、縄での結束はいたしません。
全国からもご注文いただいています。
●奉献酒(鳴門鯛 吟醸 飛切)1800ml 2本縄かけ(奉献のし) ¥5,500(税込)
●奉献酒(鳴門鯛 吟醸 飛切)1800ml 1本(奉献のし) ¥2,750(税込)
●奉献酒(鳴門鯛 吟醸 飛切)720ml 2本縄かけ(奉献のし) ¥2,750(税込)
●奉献酒(鳴門鯛 吟醸 飛切)720ml 1本(奉献のし) ¥1,375(税込)
●奉献酒(鳴門鯛 純米 巴)300ml 2本縄かけ(奉献のし) ¥990(税込)
当蔵の定番酒に「奉献」の熨斗をお付けしました。金色の巻紙の一升瓶はおめでたい場にぴったり。本家松浦酒造場の「奉献酒」をどうぞご利用ください。300ml 2本のミニサイズ奉献酒もどうぞ。
このページをご覧のあなただけにお得なクーポンプレゼント!
NARUTOTAI SHOPで奉献酒を選び、カート(1)のクーポン欄に「8888」を入力してください。奉献酒が10%オフになります。
奉献酒について まとめ
奉献酒について、おわかりいただけたでしょうか?
ここまでの内容を一覧にまとめました。
- 地鎮祭で祭壇におまつりする日本酒を「奉献酒」という
- 日本酒に「奉献」と書かれた熨斗(のし)を巻く
- 「奉献酒」は、一升瓶2本組、あるいは一升瓶1本が主流
- 場合によっては300ml、720mlなどの小・中瓶を「奉献酒」にしてもよい
この記事の監修
-
権禰宜(ごんねぎ)岩野 孝能さん、広報担当 忠津 智子さん
大麻比古神社(公式サイト) 
- 本家松浦酒造場から車で約10分ほどの場所にある、阿波国一宮の大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)。
徳島県の総鎮守として古くから崇拝されてきた県内一の大社で、大麻比古大神と猿田彦大神の二柱の神様をおまつりしています。地元では親しみをこめて「おおあささん」「おおあさはん」などと呼び、交通安全、初宮詣、家内安全などを祈願する人々が数多く訪れています。